就業規則が会社と社員を守る理由
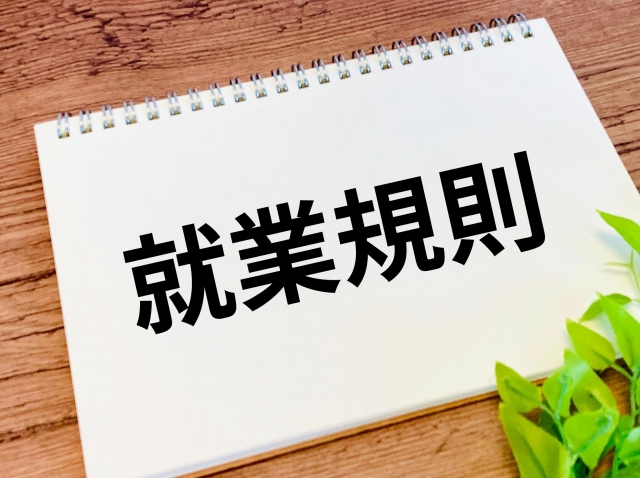
当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は、会社経営において非常に重要でありながら、「面倒」「難しい」というイメージを持たれがちな「就業規則」について、その本当の価値と意義をお伝えしたいと思います。
就業規則とは何か
就業規則は、会社における「働き方のルールブック」です。労働時間や休日、給与の支払方法、退職の手続きなど、会社と社員の関係を規定する基本的なルールを定めたものです。労働基準法では、常時10人以上の社員を雇用する事業場では、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
しかし、就業規則の価値は法的義務を果たすことだけではありません。適切に整備された就業規則は、会社と社員の双方を守る「信頼の証」となるのです。
会社を守る就業規則の役割
1. トラブル防止の防波堤
明確なルールがないと、同じような状況でも対応がその場その場で変わってしまいます。例えば、ある社員には許可した早退を別の社員には認めないといった対応をすれば、不公平感が生まれ、職場の雰囲気が悪化する原因となります。
就業規則があれば「このケースではこう対応する」という基準が明確になり、感情や個人的な判断に左右されない公平な職場運営が可能になります。これは社員間のトラブルだけでなく、会社と社員の間の紛争防止にも役立ちます。
2. 労使紛争におけるリスク軽減
残念ながら、会社と社員の間で意見の食い違いが生じ、紛争に発展することもあります。そのような場合、適切に整備された就業規則は会社の強力な味方となります。
例えば、懲戒処分や解雇の事案では、その根拠となるルールが就業規則に明記されているかどうかが争点となることがあります。明確な規定がなければ、会社側の措置が「権利の濫用」と判断されるリスクが高まります。
実際の裁判例でも、就業規則に基づかない一方的な労働条件の変更や、規定のない懲戒処分が無効とされるケースは少なくありません。会社を守るためには、適正な手続きを経て作成・周知された就業規則が不可欠なのです。
3. 経営理念の実現ツール
就業規則は単なる規則集ではなく、会社の「あるべき姿」を示す羅針盤でもあります。「どのような会社を目指すのか」「社員にどのような行動を期待するのか」といった経営理念を具体化する手段として、就業規則を活用することができます。
例えば、ワークライフバランスを重視する企業であれば、育児・介護休業の取得促進や柔軟な勤務形態について手厚く規定することで、その理念を形にすることができます。こうした取り組みは、採用活動においても会社の魅力として伝わり、優秀な人材確保にもつながります。
社員を守る就業規則の機能
1. 権利保障の基盤
就業規則は社員の権利を守る重要な役割も担っています。労働時間や休日、賃金などの労働条件は、就業規則によって明文化されることで社員の権利として保障されます。
特に、労働基準法などの法令が定める最低基準を上回る労働条件(例:法定を超える有給休暇日数や、手厚い休業補償など)は、就業規則に記載されることで初めて社員の確かな権利となります。社員にとって、これは大きな安心感につながるものです。
2. 公平性の担保
「同一労働同一賃金」という言葉が象徴するように、現代の労働環境では公平な処遇がますます重要視されています。就業規則は、昇給や昇格の基準、各種手当の支給条件などを明確に定めることで、恣意的な人事評価を防ぎ、社員間の公平性を確保します。
また、育児・介護との両立支援制度や、ハラスメント防止措置なども就業規則に明記することで、すべての社員が安心して働ける環境づくりに貢献します。これらは特に、立場の弱い社員を守るセーフティネットとしての機能を果たします。
3. キャリア形成のガイドライン
就業規則は、単に「何をしてはいけないか」を定めるものではありません。教育訓練の機会や、キャリアパスの道筋を示すことで、社員の成長を支える羅針盤にもなり得ます。
例えば、資格取得支援制度や社内公募制度などを就業規則に位置づけることで、社員は自身のキャリア形成に必要な情報を得ることができます。これは、社員のモチベーション向上と、会社の人材育成という双方の利益につながる取り組みです。
効果的な就業規則づくりのポイント
1. 「使える」就業規則を目指す
残念ながら、多くの会社では就業規則が形骸化しています。書店で売られているひな形をそのまま使ったり、他社のものを流用したりした結果、実際の職場の実情とかけ離れた内容になっていることがあります。
効果的な就業規則は、その会社の実態に合わせてカスタマイズされたものです。
例えば
- 実際の勤務形態に合わせた労働時間制度
- 会社の規模や業種に適した賃金・評価制度
- 過去に起きたトラブル事例を踏まえた懲戒規定
これらを盛り込むことで、実際の場面で参照・活用できる「生きた就業規則」となります。
2. 社員の意見を取り入れる
就業規則の作成・変更に際しては、労働者代表の意見聴取が法的に義務付けられていますが、これを形式的な手続きで済ませてしまう会社も少なくありません。しかし、本当に効果的な就業規則づくりのためには、社員の声に真摯に耳を傾けることが大切です。
社員からの意見を丁寧に集め、可能な限り反映させることで、より実効性の高い就業規則となるだけでなく、社員の納得感も高まります。「自分たちの意見が反映された」と感じることで、ルールへの遵守意識も向上するでしょう。
3. 定期的な見直しを行う
労働環境や法令は常に変化しています。特に近年は働き方改革関連法の施行や、テレワークの急速な普及など、大きな変化が続いています。そのため、就業規則も「一度作ったら終わり」ではなく、定期的な見直しが不可欠です。
最低でも年に一度は就業規則を見直し、法改正や社会情勢の変化、会社の成長段階に合わせて適切に修正していくことをお勧めします。これにより、常に最新の状況に対応した就業規則を維持することができます。
当事務所のサポート体制
当事務所では、就業規則の作成・改定に関する包括的なサポートを提供しています。
具体的には
- 現状分析:貴社の現在の労務管理状況や課題をヒアリングし、適切な就業規則のあり方を一緒に考えます。
- 法令対応チェック:最新の法令に準拠した内容になっているか確認し、必要な修正案を提案します。
- 実効性の確保:形だけの就業規則ではなく、実際の運用に即した内容となるよう、実務的な観点からアドバイスします。
- 社員への説明支援:就業規則の内容を社員に正しく理解してもらうための説明会の開催や資料作成をサポートします。
- 定期的なメンテナンス:法改正や貴社の成長に合わせて、定期的な見直しと更新をお手伝いします。
おわりに:就業規則は「信頼と対話」の基盤
就業規則は、単なる「会社のルール」ではありません。会社と社員が互いの権利と義務を理解し、健全な関係を築くための「信頼と対話の基盤」です。
適切に整備された就業規則があれば、会社は法的リスクを軽減しながら経営理念を実現でき、社員は自分の権利を守りながら安心して働くことができます。その結果、会社全体の生産性向上と、働きがいのある職場づくりが実現するのです。
当事務所では、この理念のもと、お客様一人ひとりの状況に寄り添った就業規則づくりをサポートしています。「うちの会社に合った就業規則を作りたい」「既存の就業規則を見直したい」といったご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
貴社と社員の皆様が、互いを尊重し合いながら成長していける職場づくりのお手伝いをさせていただければ幸いです。



